ゲートキーパーズの世代から
文/おでっさ
 僕は浮矢やルリ子と同じ年、即ち昭和27年(1952年)の生まれである。4月4日生まれのルリ子は僕より4日お姉さんなだけだ。
僕は浮矢やルリ子と同じ年、即ち昭和27年(1952年)の生まれである。4月4日生まれのルリ子は僕より4日お姉さんなだけだ。
この昭和27年とは大東亜戦争の敗戦から、たった7年しか経っておらず、サンフランシスコ平和条約によって、日本がようやく独立を回復した年だ。昭和25年(1950年)に始まった朝鮮戦争(1950〜1953)のせいもあって、進駐軍と呼ばれたアメリカ占領軍がまだ大勢駐留していた。僕の住んでいた横浜の伊勢佐木町には焼け残った野沢屋デパートや、松屋デパート、レストランの不二家等があったが、米軍の野戦病院や、米兵とせいぜい彼等の腕にぶら下がった娼婦達しか入れない、「日本人お断りのPX」になっていた。
僕の家の裏には彼等のカマボコ兵舎があり、軍楽隊が駐留していた。また伊勢佐木町の奥の方には、なんと軽飛行機用の飛行場まであった。
当時の日本はまだ貧しく、僕の幼児時代に住んでいた家はトタン屋根の粗末な家だった。横浜で一番の繁華街だった伊勢佐木町商店街ですらそんな有り様だった。まだ戦争の傷痕は随所に残っており、焼け跡のままの空き地や、崩れたビルや教会等の廃墟は、僕らいたずら小僧や洟垂れ娘の格好の遊び場として機能していた。アスファルトで舗装されていたのはメイン・ストリートだけで、ちょっと横道に入れば赤土むき出しの路地や砂利道が広がっていた。だから夏場は打ち水をしないと乾燥して砂ぼこりが巻き上がった。
街中を流れる川の色は工場廃液等の影響で、日替わりで七色にくるくるとその色を変え、時々人だかりがしているので、首をつっこんでみると、麻薬Gメンの土左衛門が、その変な色の水面に浮かんでいたりした。そこには黒沢映画の「天国と地獄」の世界があった。
TVのある家はまだ珍しく(無論、白黒だ)公園や、街角には街頭カラーTVが立っていて、野球や相撲やプロレス等のスポーツ中継を大勢の大人が黒山になって観戦していた。こどもの遊び場は、もっぱらゴミゴミした路地裏か、空き地だった。浮矢やルリっぺが育ったのはこんな時代だったのだ。
僕らの楽しみは小学校から戻るやランドセルを放り出して、空き地や公園で真っ黒になって、暗くなるまで銀玉ピストルや2B花火等で戦争ゴッコをすることや、毎月月初めに発売される「少年」や「少年クラブ」「漫画王」「冒険王」等の月刊誌で手塚治虫や、桑田次郎の漫画を読むことだったり、そろそろ始まったTVの「月光仮面」「ハリマオ」「鉄腕アトム(実写版)」等の白黒特撮番組を見ることだった。近所の駄菓子屋はこうした悪童の溜まり場だった。
ところで日米安保条約締結をめぐる騒乱、所謂「60年安保」の時は僕らは8才、小学校3年生だった。デモ隊の国会突入にまで至ったこの大騒動は戦後日本を震撼させた。だがそれは結局、敗戦国の一種の屈折したナショナリズムの発露でしかなかった。また冷戦の時代にあっては、反米即ち親ソという構図が成り立ってしまい、反米ナショナリズムは皮肉にも左翼の専売特許みたいになっていた。
一方、僕らの読んでいた少年雑誌は戦争の記事や戦争マンガで溢れていた。やっと敗戦の脱力状態から抜け出して自信を取り戻しつつあった大人たちは、アラカン(嵐勘十郎)主演の「明治天皇と日露大戦争」等の戦争スペクタクル映画を大ヒットさせた。けだし安保騒乱と、少年雑誌に溢れる戦記もの記事や戦争マンガ、国産戦争映画の大ヒット等には同じモティーフが流れていたのである。
 僕等は安保騒動をけっこう冷ややかな目で見ていたように思う。ゼロ戦、大和が大好きな遅れてきた軍国少年の僕等にとって、アメリカもソ連も敵でしかなかったから、親米の自民党も、親ソの社会党、共産党、全学連も、単に連合軍に尻尾を振る情けない連中にしか見えなかったのかもしれない。
僕等は安保騒動をけっこう冷ややかな目で見ていたように思う。ゼロ戦、大和が大好きな遅れてきた軍国少年の僕等にとって、アメリカもソ連も敵でしかなかったから、親米の自民党も、親ソの社会党、共産党、全学連も、単に連合軍に尻尾を振る情けない連中にしか見えなかったのかもしれない。
ちなみに後の70年安保の全共闘の世代は、僕らよりちょっと上の世代だが、戦後民主主義の虚妄と既存の社会秩序に対する不信感や、将来への漠然とした不安や、管理社会の閉塞感等が、彼等をして不毛の闘争へと駆り立てたことは容易に理解できる。
閑話休題。僕らの子供時代の最大のイベントのひとつは何といっても東京オリンピック(昭和39年・1964年)だった。それに併せて首都高や、新幹線も整備された。オリンピックを家庭で観戦するために、カラーTVが爆発的に普及した。わが家のTVがカラーになったのもこの頃だ。
日本は「もはや戦後ではない」を合言葉にかつてない繁栄の時代、高度成長の時代へと向かっていた。しかし一方では旧いものは全て悪であるという表面的で薄っぺらな価値観と、拝金主義が横行し、環境破壊や公害が進み、受験戦争が利己主義のエリート官僚の卵を多数生み出していた。
作家三島由紀夫が「大ビルは建てども、大義は崩壊し」と2.26事件や特攻隊の英霊の口を借りて嘆いたとおり、偽りの戦後民主主義の行き詰まりと狂気のバブル経済の時代の到来が予感された。そういう時代の空気の中から、あちこちで大学紛争が起り、またベトナム反戦運動が盛んになった。
しかし、インテリぶって世界同時革命を夢想する革命家や、反戦運動の闘士を気どっていた連中の多くは、所詮親の金で大学に通っていた坊ちゃん嬢ちゃんであり、自分の親が支払った税金によって作られた敷石を剥がして機動隊に投石していた。一方、機動隊の方には貧しさ故に大学には行かれず、警官になって弟や妹の学費を払っていた隊員もいた。こういう皮肉な構図が問題の不毛な本質を象徴していた。
さて子供の頃からヒトラーの研究を志していた僕は、中学3年の時に、縁あって三島由紀夫氏の戯曲「我が友ヒットラー」の上演の際の歴史考証を手伝うことになった。浮矢たち、ゲートキーパーズが活躍した1969年(昭和44年)1月18日、この戯曲は劇団浪漫劇場によって初演された。奇しくもこの日、東大全共闘が立て篭っていた本郷の東大安田講堂、通称安田城が機動隊の導入によって陥落した。それはこの戯曲の中で玩具のような第2革命を夢見たSAが国軍と手を結んだSSによって粛正されてゆく姿にオーバーラップして見えた。ヒトラーの最後のセリフはこうだった。「さうです。政治は中道を行かねばなりません。」
僕らの世代にとって、オリンピックの次の大イベントは1970年(昭和45年)、大阪の千里丘陵で開催された万国博だった。前年には、泥沼化したベトナム戦争に呻吟しつつもアメリカが国威をかけて飛ばしたアポロ11号が月面着陸に成功し、人類が月に立っていた。ベトナムというホットウォー地域を抱えた米ソの冷戦が、いつ本物の核戦争に発展し人類が滅亡するかもしれない危険の中で、万国博は無事開催され成功裏に終了した。この万博のスローガンは、皮肉にも「人類の進歩と調和」というものだった。
原作者の山口氏がインベーダ−という存在に何を仮託したかったか、直接伺った事は無いが、TVアニメ版の最終回のシナリオによれば、それは宇宙からの侵略者などではなく、人間の欲望を喰らって増殖する擬似生命体であるという。ゲートキーパーズ世代の僕には、このインベーダ−こそ、戦後日本に巣食う屈折して歪んだ近代合理主義や、それを糊塗補完するために常に利用されてきた戦後似非民主主義、似非日本国憲法等、この国の抱える数々の矛盾や問題点の象徴のように感じられる。
同年の11月25日に僕が親しくしていた作家・三島由紀夫が、戦時中は陸海軍の大本営が置かれ、戦後は一転して東京裁判の舞台ともなった自衛隊市ヶ谷駐屯地1号館にて、戦後日本に対してワンマンウォーを挑んで「玉砕」した。
|
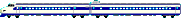 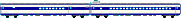 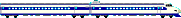
|